経団連は1月27日、東京・大手町の経団連会館で危機管理・社会基盤強化委員会首都直下地震等対策推進タスクフォース(光田毅座長)を開催した。実効的な事業継続計画(BCP)の策定に向けて検討を深めるべく、MS&ADインターリスク総研の山口修リスクマネジメント第四部長、セブン―イレブン・ジャパンの中澤剛リスクマネジメント室エキスパート(日本フランチャイズチェーン協会大規模災害対応共同研究会座長)から、それぞれ説明を聴くとともに意見交換した。説明の概要は次のとおり。
■ 大規模災害等に向けたこれからの企業BCPのあり方(山口氏)

目指すべきは「何があっても『臨機応変』に対応できるBCP」であり、(1)臨機応変対応(2)戦略オプション(3)安全配慮義務――に着目すべきである。
(1)については、行き当たりばったりの対応にならず、収集した情報を基に戦略や手順を適宜組み替えて動くことが重要になる。そのためには事前(方針策定や分析)・事後(訓練や見直し)の工程もきちんと計画を策定し、事業継続マネジメント(BCM)のサイクルを回すべきである。
(2)については、被災拠点の早期復旧を待たずにBCP目標を達成する戦略(代替戦略、在庫戦略、他社連携戦略等)も検討すべきである。その際、事業の内容や業務の進め方を改めるトランスフォーメーション戦略の採用も考えられる。このような戦略は災害の種類を問わない「オールハザード型BCP」と親和的である。しかし、戦略構築に手間やコストがかかるので、企業価値向上につながるといった社内的に納得できる工夫が必要だろう。同時に、サプライチェーン一体となった取り組みも必要である。
(3)については、災害時でも従業員や来客者らの生命・身体の安全に配慮した判断を的確に下せるようにすべきである。正解がない臨機応変な判断が求められるため、収集する情報や判断のオプション等「判断のプロセス」を準備しておくことが重要である。そして、実際は拠点統括が判断するため、各拠点が自走できるようルールを周知徹底することがカギとなる。
■ 実務的観点からの災害対応(中澤氏)
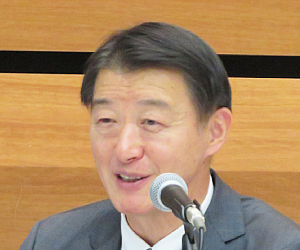
セブン―イレブン・ジャパンでは、お客さまや加盟店、サプライチェーンも考慮したBCPを策定している。災害時には、迅速に店舗を復旧・再開して在宅避難者に物資を供給するとともに、協定に基づき自治体避難所に支援物資を届け、地域社会に貢献している。
2021年に従来のBCPを見直し、図上演習で検証しつつオールハザード型BCPを策定した。この図上演習直後の大型台風対応では演習どおりに行動し、早期の計画休業の判断、従業員・配送ドライバーの安全確保、食品ロスの削減に役立った。この経験でBCPの重要性を改めて認識した。BCP策定後、毎年、実際の災害対応や演習の教訓を検証し、改善につなげるPDCAサイクルでBCMを実践している。
21年から3年間、日本フランチャイズチェーン協会主催でコンビニ5社が中心となり、省庁・自治体と共に大規模災害対応共同研究会を開催した。首都直下地震、南海トラフ地震発生時に全ての被災者に迅速に必要物資を届ける――という共通目標のもと、大規模災害の課題や解決策を検討し、25年1月に最終報告書(注1)を公表した。
首都直下地震では、店舗や工場の損壊、配送機能の低下が予想される。これらへの対応については、緊急通行車両確認標章の事前交付、燃料の優先給油対象であることの確認等、国や自治体の協力で一定の成果が得られた。他方、道路啓開(注2)、ライフラインの回復、輸送力の総合調整、トイレ提供等は引き続き検討課題として残った。例えば、川崎市・東扇島の冷凍倉庫群が長期間停電すれば、原材料が腐敗し、食料供給に多大な影響を及ぼす。
最終報告書では、能登半島地震の教訓も踏まえ、自助のための「ローリングストック普及キャンペーン」を国・自治体・コンビニ7社が協力して行うこともうたっている。各家庭で最低3日、可能なら1週間分の備蓄を呼びかけているが、一人ひとりが備えることにより被災地への食料供給負荷を低減できるので公助の観点からも有用である。
(注1)日本フランチャイズチェーン協会主催 大規模災害対応共同研究会 最終報告
https://www.jfa-fc.or.jp/misc/static/pdf/202501-final-report.pdf
(注2)道路の障害物等を取り除いて、通行できるようにすること
【ソーシャル・コミュニケーション本部】


