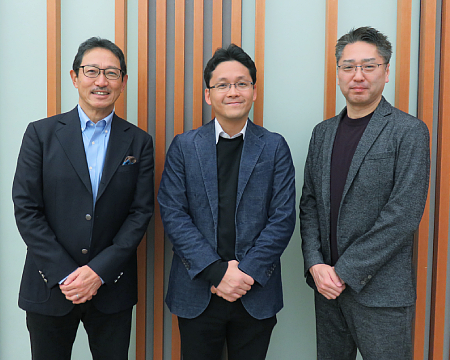
左から杉本氏、木村氏、五十棲氏
経団連では、提言「スタートアップ躍進ビジョン」(2022年3月)で掲げた、27年までにスタートアップの数・成功のレベルを共に10倍にするという目標「10X10X」の実現に向けてさまざまな活動を展開している。
なかでも重要な活動の一つが、第3回を実施中の「スタートアップフレンドリースコアリング」(スコアリング)である。
経団連は1月30日、東京・大手町の経団連会館で、スコアリング参加企業への特典として、新たなイノベーション手法として注目を集める「ベンチャークライアントモデル」(VCM)に関する勉強会を開催した。デロイト トーマツ ベンチャーサポートの木村将之COO、Honda Innovationsの杉本直樹CEO、FUJIの五十棲丈二社長を講師に招き、VCMの特徴や実践について説明を聴いた。概要は次のとおり。
■ VCMの特徴(木村氏)
<定義と効果>
VCMとは、企業がスタートアップの顧客となって、そのプロダクトやサービスを利用し、売り上げ向上やコスト低減といった戦略的利益を実現する一連のプロセスを指す。ドイツのBMWで開発され、ボッシュやシーメンス、フランスのエアバス、トタルエナジーズなどの世界的企業が取り組んでいる新たなイノベーション手法であり、日本企業でも導入が進みつつある。
スタートアップにとっては、企業との共同開発ではないため、知的財産の取り扱い等に関するトラブルの心配がなく、顧客を獲得しながらプロダクトに対するフィードバックを得られるというメリットがある。
VCMでは、戦略的な利益に基づく企業の目的が取引前に明確になっているため、本格導入に至る成功確率が非常に高くなる。またVCMでは、検証を経てさらなる開発が必要と判明すれば、企業との共同開発へと進展することもある。この場合、一度顧客となってどの部分を開発すれば良いかを互いに確認できているため、共同開発自体の成功確率も高くなる。
<他の手法との比較>
VCMはスタートアップの技術・サービスを迅速に購入・検証することに特徴がある。従って、短期での新製品開発やオペレーションの改善等が目的である場合にVCMは効果を発揮しやすい。
コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)やM&Aも有効な手法だが、VCMとの違いに留意する必要がある。
CVCはスタートアップへの出資を通じて、ビジネスアイデアや市場動向に関する深い知見が得られるが、時間軸はVCMよりも長く設定される。
M&Aは相手企業を自社内に取り込むため、技術やビジネスを独占的に活用できるメリットがある。しかし、買収にかかるコストや、競合他社による敬遠に起因する技術発展の停滞といった懸念も存在するため、これらの論点も併せて検討する必要がある。
総じて短期の成果創出に主眼を置く場合、VCMは有効な手法といえる。
■ VCMの効果を最大化するコツ(杉本氏、五十棲氏、木村氏によるパネルディスカッション)
スタートアップとの協業について、杉本氏はイノベーションを有する企業との連携による企業変革の加速、五十棲氏は検証や開発のスピードアップと効率化を求めると述べた。
杉本氏は、自社の新規事業領域でスタートアップとの協業が複数開始したことを契機に、徐々に既存事業にもスタートアップ連携が波及していったと振り返り、五十棲氏もこれに呼応。同時に、事業部門ではなくイノベーション部門の予算を用いて初期PoC(Proof of Concept)を実施することが、インパクトを生み出しやすい既存領域で連携を進めるコツと説明した。
さらに、五十棲氏はVCMのメリットにスピード感を挙げ、自社の求める基本仕様を充足することをVCMによっていち早く確認した後、性能・品質を向上させていった事例を紹介した。杉本氏は、VCMによって技術を確認したうえで、共同開発や本業への取り込みへと進む道もあることをメリットとして挙げた。
【産業技術本部】
経済界全体の行動変容を促し、日本経済をさらに活性化させるべく、2022年度から開始しました。第2回までで約200社にご参加いただいています。
企業は、計38問のアンケートに回答することで、スタートアップエコシステムに関わる自社の活動を数値化したレポートを受け取ることができます。個社の回答内容(回答内容、結果の数値・ランク等)は完全非公開。ただし、参加企業名およびトップ10社は、経団連ウェブサイトで公開しています。
スコアリングに参加することで、自社の取り組みの分析・改善、社内における取り組みの可視化、プレスリリース等による対外PR、回答企業限定の勉強会への参加等が可能となります。
ただいま、第3回スコアリングを実施中です(回答期限:2月28日)。ぜひ回答をお願いします。


