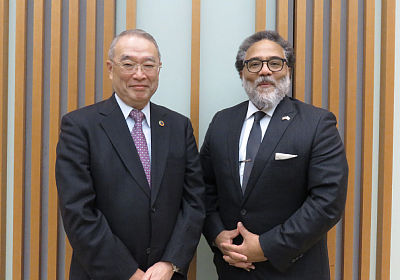
コーカー氏(右)と遠藤委員長
経団連のサイバーセキュリティ委員会(遠藤信博委員長、金子眞吾委員長)は、米国ホワイトハウスのハリー・コーカー・ジュニア国家サイバー長官が来日する機会を捉え、12月6日、東京・大手町の経団連会館で懇談会を開催した。コーカー氏から、サイバーセキュリティ強化に向けた取り組みについて説明を聴くとともに、活発な意見交換を行った。概要は次のとおり。
■ コーカー氏説明
米国では2021年に発足した国家サイバー長官室(ONCD=Office of the National Cyber Director)のもと、23年に国家サイバーセキュリティ戦略を策定し、官民連携や同盟国との連携を推進している。また、ONCDが連邦政府の中核として関係省庁との調整を行う一方、「デジタル連帯」(digital solidarity)の構築に向けて日本等の同盟国や産業界との協力を進めている。
AIや量子コンピューティング等、最先端の技術が急速に発展し、重要インフラへのサイバー攻撃がサプライチェーンに甚大な影響を及ぼすなか、増大するサイバー脅威に連帯して対処することが極めて重要である。
■ 意見交換
(1)官民連携
経団連側から米国の官民連携の具体的な取り組みに関して質問したところ、コーカー氏は、「JCDC(Joint Cyber Defense Collaborative)(注)で官民の情報共有を促進している。例えばロシアによるウクライナ侵攻に際しては、バイデン大統領の指揮のもと、平時は公開しないインテリジェンスを広く共有した。当該情報を基に同盟国の官民が連携し、サイバー攻撃に対処した」と具体例を紹介した。また、「本来セキュリティの強化に時間を割くべき企業の最高情報セキュリティ責任者(CISO)が実際には規制やコンプライアンスの確認に大半の時間を費やしている現状を踏まえ、事業者の目線から規制・制度の調和にも取り組んでいる」と述べた。
(2)人材育成
経団連側からサプライチェーン全体の防護に向けた人材育成の取り組みについて質問したところ、コーカー氏は、「サイバー人材について、約50万人に及ぶ求人を米国で行っているが、十分確保できていない」との課題認識を示したうえで、人材プールを拡大するため実施している大学生との対話を披露した。さらに、「学生たちはサイバーセキュリティ関連の業務に従事するためには理工系学位が必須と認識していた。しかし実際には、理工系学位よりも、好奇心を持って集中して業務に取り組める人材であることが重要」と、人材確保に向けた抱負を語った。
■ AI×サイバーのルール作り
コーカー氏は、「サイバー空間では自主的な規制が尊重されているが、サイバー攻撃が多発するなか、現行規制では不十分との議論もある。自主規制のもとで開発・利用が進められているAIについても、サイバー同様の道をたどるかもしれない」と発言した。これに対し遠藤委員長は、「AIに関する現行の規制はソフトローが主流だが、指摘のとおり、今後の状況によってはハードローにならざるを得ない可能性もある。責任あるAIについて、ユーザー等を含めた日米のマルチステークホルダーで今後とも議論を深めていきたい」と述べた。
◇◇◇
経団連は今回の議論も踏まえ、日米サイバー協力の一層の強化に向けて、サプライチェーン全体を俯瞰したレジリエンス強化や人材育成等に資する実効的な官民連携の取り組みを強化していく。
(注)米国サイバーセキュリティ・社会基盤安全保障庁(CISA)によって21年に設立された官民の共同サイバー防衛連携
【産業技術本部】


