経団連(十倉雅和会長)は、企業行動憲章の会員企業・団体への理解浸透を目的に「企業行動憲章シンポジウム」を毎年度開催している。8回目となる2024年度は2月3日、東京・大手町の経団連会館で、「責任あるデジタル技術の開発・利活用」をテーマに開催した(オンラインで同時中継)。概要は次のとおり。
■ 開会あいさつ
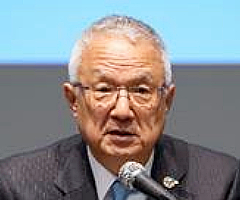
中山委員長
冒頭、中山讓治企業行動・SDGs委員長があいさつ。同シンポジウムのテーマに関して、デジタル技術の急速な発展と普及が進むなかで、企業は法令遵守のみならず、倫理に基づくデジタル技術の開発と利活用が求められている状況だと説明。また、企業行動憲章を巡る最近の経団連の取り組みや、責任あるAIの開発と利活用に関連する企業行動憲章の条文(「第1条 持続可能な経済成長と社会的課題の解決」「第3条 公正な情報開示、ステークホルダーとの建設的対話」「第4条 人権の尊重」「第5条 消費者・顧客との信頼関係」)について紹介した。
■ 基調講演「『責任あるAI』の開発と利活用」

津賀副会長
津賀一宏副会長は、パナソニックにおける「人間中心の責任あるAI利活用」推進に向けた取り組みを紹介。AIに対する向き合い方として、基準で守る「安全」と、倫理で守る「リスク管理」の必要性を説明した。
また、AI倫理を重要な課題と捉え、全社員への啓蒙・ガバナンス体制を構築していることに加え、今後の未知なる社会づくりに挑戦していることを述べ、「社会・技術の変革に、ルールメーキングと価値創出で貢献していく」と言及した。
■ 講演「デジタル技術の利活用における倫理の役割」(岸本充生 大阪大学D3センター教授)

岸本氏
企業がデジタル技術を含む新しい技術を社会実装したところ、安全性やプライバシーの確保等を巡り「炎上」する事例が発生する一方、「何かあったらどうするんだ」という考えから、何も新しいことができなくなる問題も発生している。いずれも、技術と社会の間のギャップを埋めるノウハウが欠如していることが原因である。解決に当たっては、ELSI(Ethical, Legal and Social Issues、倫理的・法的・社会的課題)の考え方が重要である。
法規制(L)が技術革新の後追いにならざるを得ない、世論(S)の動向も読めない不確かな時代には、企業は自ら掲げる倫理規範(E)を羅針盤とし、それに沿っていることを示すことが求められる。また、技術・製品・サービスについて、社会実装前にリスクを評価し、対策を実施したうえで、倫理面において許容できないリスクがないことを自ら示す、リスクマネジメントが必要である。
■ パネルディスカッション

パネルディスカッション
秋池玲子企業行動・SDGs委員長をモデレーターに、富士通の時田隆仁社長、ユニ・チャームの高原豪久社長、中外製薬の大内香上席執行役員が登壇し、各社の取り組みをそれぞれ紹介した。登壇者の発言要旨は次のとおり。
(時田氏)
「AI倫理は経営課題」との認識のもと、AI倫理外部委員会を設置し取締役会にも共有している。データ・AIのさらなる活用、適切なルール形成や国際協調が実現されるよう、企業・産業界として、企業経営の高度化、ユースケース創出、価値を共有するコミュニティづくりが重要である。社会が安心してAIを活用できるための技術研究を推進している。
自律的に課題解決を実行する「AIエージェント」と協働する社会に向けて、新たな脅威へ対応するためにも倫理やルールの不断の見直しが求められる。
(高原氏)
女性の健康管理アプリの運用において、AIリスクを抑制するため、誤回答など、リスクのあるAIチャットによる回答をプロアクティブに検知するほか、AI回答の評価ボタンを実装することでユーザーからのフィードバックを促進している。また、苦情やトラブル発生時の業務フローを構築している。
今後は、顧客との接点拡大と顧客の深層心理の把握という2軸で生成AIの活用を推進し、他社や異業種等とのアライアンスの構築につなげていく。
(大内氏)
生成AIの活用に向けて、汎用ツールを迅速に導入し、創薬で積極的に活用できる環境を整備するとともに、デジタルコンプライアンスやAIガバナンスの推進により、安心して活用できる土壌を構築している。
革新的な価値を創出し、提供していくためには、自社の強みとデジタル活用の組み合わせを考えることが重要である。加えて、イノベーションに乗り遅れないためには、局面を大きく見たうえで、患者へのリスクを除く一定のリスクを許容する姿勢が必要となる。
(秋池委員長)
倫理に基づいてデジタル技術の開発と利活用を進めるに当たっては、そもそも「倫理観」自体がどのように形成されるかという視点も重要である。企業は「倫理」や「責任」をより俯瞰的に捉えて行動していくことが求められる。
【ソーシャル・コミュニケーション本部】


