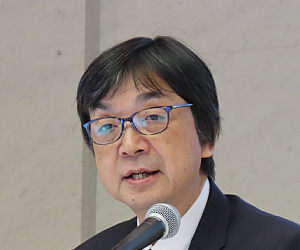
千葉氏
経団連は2月5日、東京・大手町の経団連会館で常任幹事会を開催した。東京農工大学の千葉一裕学長が「自然資本に基づく事業価値創出への挑戦」と題して講演した。概要は次のとおり。
■ 生物多様性の危機と自然資本保全の重要性
生物多様性に支えられた自然は、現代社会の基盤を形成する豊かさを人間に提供しているが、人間による経済活動が原因となって、生物多様性は急速に失われ続けている。特に、自然や水資源に恵まれているとみられている日本であっても、実は、食品や工業製品の輸入などを通じ、国内で消費される水利用の国外依存度は、世界で最も高い水準にある。こうした輸入依存度の高い状況は、食料などの安定供給の観点はもとより、環境保全や、経済安全保障の観点からも大きな課題である。
■ 生物多様性・自然資本保全に基づく新たな企業活動
他方、こうした社会課題の存在は、新しいビジネスチャンスとも捉えられる。革新的な科学技術の開発を通じ、社会の負の要素を削減することで、市場価値をもたらすことにつながる。例えば、地球温暖化対策の観点から、二酸化炭素やメタンガスの削減が求められるなか、樹木の高度利用による二酸化炭素の吸収や、土壌における炭素貯留など、生態系全体で捉える形で、農林水畜産業とバイオ燃料生産の連携による技術革新は、大きなビジネスチャンスとなり得る。
新しい技術の開発・普及に際しては、産学官の連携が不可欠である。すでに、国際的な産学官連携によるエネルギー・食品供給事業の開発が進むなど、各種の取り組みが進められている。
■ 大学を含めた異分野・他機関連携による事業価値の創出
革新的技術を用いて社会課題を解決する新しいビジネスを進めるに当たっては、大学がその先頭に立つ覚悟が不可欠である。私自身、2005年に自らの研究成果を活用する形で、ペプチド医薬原料製造のスタートアップを立ち上げ、国際的な事業へと成長させた。こうした経験から、大学の役割として、学術研究や論文発表といった従来学生に求めてきた能力のみならず、事業に挑戦するマインドを持ち、対外的な人脈形成や折衝といったビジネスに必要な能力を備える「Enablers(イネーブラーズ)」を育成することが求められると強く感じている。
食料安全保障の確保や、自然資本保全などの領域において、日本の研究力や技術力をベースとして、事業価値を創出することは可能と考えている。こうした観点から、これまで以上に産業界と大学との連携を強化していきたい。
【総務本部】


